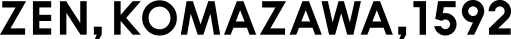ZEN,KOMAZAWA,MOVIE
第4回はゲストに映画監督の大森立嗣さんを迎え、永井総長、各務教授の3人で監督の作品を中心に『禅と映画』をテーマに鼎談。
本大学のOBである大森監督は、学生時代の環境がとても有り難かったと振り返ります。
監督の作品と禅を絡めながら、人生や人の死について考えさせられる時間となりました。
※この対談は、2019年11月14日(木)に行われた『日々是好日』の上映会に際して収録したものです。
大学時代から映画の世界へ
各務:おいでいただきましてありがとうございます。
各務:大森監督から自己紹介をお願いします。
大森:映画監督の大森立嗣といいます。
各務:よろしくお願いいたします。
大森:駒澤大学をだいぶ前に卒業しまして、映画をつくっています。今日はちょっと慣れないですけど、楽しみにしていますのでよろしくお願いします。
各務:大森監督は文学部社会学科のご卒業ということで、大学時代は「8ミリ映画同好会」にいらっしゃったということですので、今日は楽しみにしておりました。それでは永井総長、一言お願いいたします。
永井:永井です。今日はありがとうございます。
永井:私も駒澤大学仏教学部禅学科の卒業で、2年半ほど前、定年を迎えまして、いったんは学園を去ったのですが、いろんなご縁で10月から総長として務めざるを得なくなった。その中での大森監督とのこの会でございますので、不行き届きですけど、どうぞよろしくお願いします。
大森:こちらこそ、よろしくお願いいたします。
各務:本日ファシリテーターを務めさせていただきますのは、駒澤大学のグローバル・メディア・スタディーズ学部教授をしております、各務と申します。よろしくお願いいたします。

各務:それではまず最初に、大森監督の駒澤大学時代のエピソードを少し伺いたいと思います。文学部をご卒業されたと先ほど申し上げましたけれども、入学して初めて8ミリ映画同好会に入られたと?
大森:入りました。
各務:これは1年生の時になぜ入られたのか。また、それがなぜ今のこのお仕事のきっかけになっていらっしゃるのか。是非そのあたりのお話を伺わせていただきたいと思います。
大森:これがなかなか難しくて。僕、1浪して駒澤大学に入学したんですけど、高校生の時は空手をちょっとやってたりして。
大森:あんまり文化的なものに触れることが少なくて。また父親が前衛舞踏をやったり、舞台で演劇をやったり、映画にも出たりしていたんですけど、若い頃は父親に反発もあるしで、逆に「そういう芸術的なものから離れていたい」みたいな感覚がすごいあったんですけど。大学に入って、(その感覚が)ふーっと何もなくて。何が自分がしたいものなのか、まったく分かんなくなっちゃって・・・。やっぱりその中でこういうことを思い返したり、時々文章に書いてくれと言われたりするんですけど、はっきりした明確な動機が自分でもよく分からないんですよ。
各務:そうですか。
大森:ただ映画のサークルの先輩たちに、いわゆる新歓の勧誘をされて。
大森:いろんなサークルにされたんですけれど、
大森:テニスとか、野球とか、いまいちしっくりこなくて。その中でなぜか映画のサークルへ。
各務:スポーツから離れて?
大森:そう。スポーツはなかなか、才能ももう限界があるじゃないですか。
各務:空手の前も、野球をやっていらっしゃったと。
大森:やってました。駒澤大学はスポーツがすごく強くて、全国から強い人たちが集まっている部分もあるので、僕なんかは才能がなかったんです。スポーツに関してはやっぱり限界があるので。
各務:そうですか。
大森:そういう意味ではある意味、ちゃんと挫折していれたので、もう一回ふっと我に返った時に、なぜか映画を選んだんです。父親の影響がたぶんあるんでしょう。
各務:そこがやっぱり、人生の転換期?
大森:転換した気がしましたね。それで、大学に入るとやれば楽しくて。映画作りが。自分が触れたことがない世界だし。映画なんていうのは、子どもの時に見てた『ランボー』とか、ジャッキー・チェンとか、そういうのばっかり見てたんで。だから先輩たちから教わる映画も目新しいし、最初の頃はまったく意味も分からないし。だけど、映画を作ることにもう夢中になっていったんですね。周りにも感化されながら、そうこうしてるうちに大学生活なんてあっという間ですから。
各務:けっこう自主映画みたいなものを大学時代につくられて。
大森:作ったり、出たり。
各務:同好会ですものね。
大森:発表会があったり。
各務:8ミリの撮影機器があるわけですからね。
大森:当時、8ミリフィルムというものはなかなか大変で。でも、今は全部デジタルになっちゃうと、何に撮ってるかよく分からない。実体がないので。フィルムというのはそこに物体があるので、
大森:「ここのこの24コマーー、
各務:ここはカットしよう」とかね。
大森:18コマで1秒なんだと、肉体的に分かるんですよね。感覚として、映画が。
各務:なるほど。それは基礎としていいですね。
大森:そうなんです。だからいい時代だったし、いい経験ができたんじゃないかなって思うんですけどね。
各務:それが今のお仕事のきっかけで、ずっと映画界にいらっしゃるわけですからね。今の大学生にとってみても、サークルがきっかけとなって一生続ける仕事になるかもしれない、というのも有り得ますよね。
大森:そういうのはもちろんあるんでしょうけど、なかなか勇気が要りますよね。僕、就職活動とかしなかったので。
各務:卒業される時も映画同好会をやっていらっしゃって、その後は?
大森:ずっといました。
各務:また、映画で俳優をされていた時もある、と。
大森:舞台やったりしだして。
各務:これ(映画)を仕事にしようと思われたんですね。
大森:仕事にしたかったんですけど、映画の世界というのはなかなか難しいところもあるので。格闘しましたけど、ただ、根拠のない自信はあったかな。
各務:なるほど。
大森:あんまりできないと思ったことがなかったんですよね。

大学の環境が与えた、意外な影響
各務:当時を『日日是好日』の映画と関連付けるとすれば、仏教関連の授業を取られていたと。駒澤大学では、どの学部の学生さんも仏教関連の授業は必修科目なので、
各務:宗教学1、2って取っていらっしゃると思うのですが、覚えていらっしゃいますか?
大森:何となく覚えているんですけど。でも、普通にキャンパス歩いていればいっぱいいるじゃないですか、お坊さんが。
大森:お坊さんの学生たちも。
永井:そうですね。
大森:(頭を)丸めている子たちもいるし、留学生も結構いたんですよ。洋服も袈裟(けさ)なんか着てる子もいたりして、そういうのが結構日常的にあって。
大森:すごく良かったですよ。
各務:そうですか。
大森:サークルの中には仏教学部の子がいたりもしたので、お寺の先輩とか後輩もいてそういう話も聞けるし、永平寺にいた人も知り合いではいますし。
大森:(学生手帳に)『般若心経』が書いてあるじゃないですか。
永井:そうです。
大森:俺、ちょっと授業がつまんない時にずっと『般若心経』を読んでいたんですよ。意味も分からず。そしたら、半分ぐらい頭に入っちゃって。
永井:いいじゃないですか。
各務:それは素晴らしい。やっぱりありますよね、環境というのは無意識のうちに。
大森:今日久しぶりに学校に来て、購買に行って、写経のあれ買ったんです。
大森:仕事が忙しいと、無になれるかなと思って。
各務:意識的ではなく、環境を整えるというか。
大森:好きなんですね、割と。ただあんまり接点がないので、むしろ今日お話を・・・総長ということで焦っていますけど。
永井:いやいや、そんな難しい話はしません。
大森:でも、お人柄が素晴らしくて安心しています。
各務:総長は大森監督が学生だった時代、文学部の学生さんに必修科目を教えていらっしゃったとか。
永井:私は法学部や経済学部でしたね。
永井:仏教学部の学生というのはそんなに多くなくて、他の学部の方が圧倒的に多い。今は情報化社会だからちゃんと見て、駒澤は宗教系・仏教系だと分かって入ってくるでしょうけど、私が昭和40年4月に入学式に来たら、隣が経済学部の学生さんで。最初、入学式で『般若心経』を読んだら、大きい声で「ここは坊主の大学か!」って言って。よく調べてこいよって言いたかったんですけど、ともかく、そういう人が(駒澤には)ずっとたくさんいらっしゃるから。我々、教える側にも責任があるんですけれども、やはり何も知らない人たちにどうやって興味を持ってもらって、日本文化の中でこんなにも宗教、あるいは仏教というのは意味があるんだということを、伝えてあげないとですね。意外とみんな関心はあるんだけど、どこが取っ掛かりになるのか。それが問題なんです。
各務:そうですね。でも、今でも(般若心経を)覚えていらっしゃるということは、当時意識的じゃないにしろ何かやはり・・・。
永井:そうなんです。だからよく仏教の話というのは「寝ていても毛穴から入る」と言うんですよね。寝ていてもいいんだ、と。もちろん冗談ですけど、
永井:でも、そういう言い方もあるので、やはり”雰囲気”で覚えていく。そして、それはとても大きいのではと思います。強制的に教えることは、試験のために教えるというだけになってしまうので。人間を教育するという意味ではやはり、「何となく昔教わったような・・・」というぐらいでいいと思うんです。だから、私は個人的に仏教学部でなくても「昔、仏教を教わったな」というのを、例えば70、80になった頃やもっと若い頃、悩んだ時の手立てとして一つあるぐらいが一番良いのではないかと。プロになりたければ、本当に頭丸めて修行してこいよという話になるでしょうけど。
各務:学生手帳で『般若心経』をつらつら見てたというのは、素晴らしいですね。
永井:そういう学生さんは少ないと思いますよ。
各務:今でも記憶に残ってらっしゃる、という環境が素晴らしいと思います。

『日日是好日』にまつわる故事
各務:この辺りで『日日是好日』と『タロウのバカ』について、お話しさせていただきたいんですけど。
大森:ありがとうございます。
各務:『日日是好日』。先ほど上映会をさせていただいて、大変盛況で。
大森:ずいぶんと入っていましたね。
各務:永井先生からまず「日日是好日」の禅の言葉、これについて本来どういった意味があるのかということを少し。
永井:あの言葉自体は確かに幅のある理解の仕方があって、「今日も雨だった。雨でもいい天気だった」というふうに(解釈する)というのをどこかに書いてありましたけど、実はもっとどろどろした世界があの言葉の中にはあるんだろうって、私個人的には思っています。
遣唐使の”唐”(の時代)が終わって”宋”になる間、中国が大きく5つに分かれる時代の一番南、今の広東省辺りにあった”南漢”という国がスポンサーになってやった雲門というお坊さんがいたんです。このお坊さん、生まれは元々上海の近くの”嘉興”という所で名門の出なんですが、なかなか素直にいかなかった。(雲門には)偉いご先祖様がいるんですけど、変わっていまして。家の人にも告げずに友達に誘われたというので、戦争に行くんですね。それで、ある時ふと思い出す。ジュンサイとマコモ、それからスズキのなますを。これが嘉興の名物なんだけど、「それが食いたくなったから俺はもうやめて帰る」と。結局引き上げてしまう。周りの人が「あなた、名誉のほうが大事だろう」と言っても、「名誉より一時の食欲のほうが大事だ」というような意味合いのことを言って。そういう事実は中国の正式の歴史書に載りますので、みんな(雲門の先祖の話を)知っている。「あそこのあの末裔だぜ*」と。(なので雲門は)立身出世よりももっと別のことを考えるような生い立ちだったんじゃなんじゃないかと思うんです。
永井:最初に(雲門が)付いたのは禅宗の有名なお坊さんなのですが、その人の教育が非常に厳しかったものですから、片足に障害を負って。これ(障害を負った状態)も一人前のお坊さんとして見てもらえない時代でしたから、そこでまたハンディキャップを背負う。そんなことをしているうちに、自分の生涯の師と定めた人は、「母親の面倒を見るから、俺、坊さん辞めるわ。」と言って抜けちゃうんですね。そうすると頼りの師匠がいませんから、どうしたらよかろうというので、今度は福建省へ行く。1つ山を越えたところが福建省なのですが、そこへ行ってももうそこでは大きなお寺があって堂々とやっていますから、よそから来てもあまり居心地は良くない。結局、全国を回りながら広東省で落ち着くのですが、現在でも広東語というものは全く北京語と違うような音で、何を言ってるかよく分からないし、片言ぐらいしか喋れなかったかもしれない。(雲門は南漢に)難しい話をしたって分からないだろう、と。でも、スポンサーだから時には頭下げなきゃいけないこともある。
大森:なるほど。
永井:そうすると生まれもそうだし、勉強をしている時もそうだし、お寺を抱えてもそうだとなると、なかなか難しい人生を歩んだな、と。そもそものこの言葉というのは「今日が15日だとするならば、今日までのことはいい。これからのことをお前はどうするんだ?」と弟子に聞いたら、弟子は黙って答えられなかったので、その時に自分(雲門)が「日日是好日」と言ったというのがストーリーなんですけれども、その時の日日是好日は「今日はいい天気だよな」というぐらいのものはなくて、それこそどろどろしたものを全部抱えて言わざるを得ないというのが、日日是好日だろうと思っているんですね。
今は人間が苦しんでいる時代
大森:今ちょっとお話を伺ってて思ったんですけど、やはり面白いと思ったのは”ドロップアウト”するじゃないですか。ある種、お坊さんで。僕が青春を送ってきた時は、まだ経済が拡大再生産できていた時代なんですけど、今はもう人口はどんどん減っていくし、資本主義がはっきり言って行き詰まっている状態じゃないですか。その中で立身出世とか、ものすごい向上心を求められたりとか、それにみんな結構、今、苦しんでいるんですよ。
永井:だと思いますね。
各務:そこには答えがない、というね。
大森:そう。答えがなくて。でも、経済が最優先していく論理みたいなものにちょっとみんな疲れているのに、そこから逃れられなくなっている感じがしていて。その中でお茶室とか、ふーっとこう、自分を見つめるとか。
各務:型から入ってみる、という。
大森:形から入ってみるのもそうだし、
大森:あと、社会とは別のどこか”生”とか”死”というものがある空間じゃないですか、お茶室なんかも。ほとんど自然物でできていますもんね。
永井:そうですね。
大森:四季を感じる、ということもそうですから。
大森:僕は今むしろそういうものを、今後映画を作っていく時にずっと考えてるテーマではあるんですよ。
各務:なるほど。
大森:それは共通しているものでもあるんですけど。

永井:みんな同じ方向を見ていて、それがいいというか、右肩上がりの良い方向だとまだ許せるんだけど、右肩でもないのに同じ方向を見ざるを得ない。ある意味では異端と言うか、それから外れた人間はちょっと排除されるような議論ってありますよね。私は学校にまた戻って来ましたけれども、東京は確かに情報量も多いし、若いし、良いといえば良いのですが、田舎へ帰って芋を作っているのもいいよな、と感じていたんですね。ただ、そればっかり言っていると叱られそうだから言いませんけれども。もっと多様性を認めるような、サラリーマンも必要だし、工場で働く人も必要だし、あるいは農業をする人も必要。みんな同じような価値観でいく必要なんかまったくないと思っているんですよね。
各務:ダイバーシティ・マネジメントですね。「ダイバーシティ」「インクルージョン」「マネジメント」なんて、横文字ばっかりになってきましたが、やはり多様性の中で生きていくということですよね。大森監督はここのところ1年に1本以上作品を出されていて、暴力的なものがあっても、『日日是好日』のように静寂な映画もあって。撮っておられる軸はどのあたりかな?と想像するのですが、全体の中での『日日是好日』の位置付けは、どんな感じなんでしょうか?
大森:難しいね。
大森:基本的には同じなんですけど、表現の見せ方が違うだけなので。僕の中では。
各務:そうすると、表現のバラエティーに多様性を出したいというような意図はおありでしょうか?今回はこれでいこう、というような。
大森:それはまず、作品を読んだ時面白くて、これを自分はできるのかどうか、という。原作物であれば。
各務:このトーンでいけそうかなのか、という?
大森:いや。もっと素直に最初はこの小説、原作、エッセイでも”面白いと思えるかどうか”。そしたら、自分が一読した時”それの何を一番面白いと思ったのか”。それから、”これを脚本にする時の引き出しを俺が持っているのかどうか”ということ。
各務:割と最初の感性なんですね。
大森:一読目がすごく大事。
大森:放っておくといろんな情報が入ってきたり、いろいろ言われたりするので。やはり最初は自分が素直に思ったことを大事にしないと。映画は1本脚本を書いてから、公開までに3年とか4年ぐらいかかる時があるんです。そうすると、自分に強い何かを持っていないと、みんなを引っ張ったまま終わり切れないんですよね、ぼやけちゃって。それには自分が最初に「これが大事だな」と思うことが必要ですよね。
各務:そうすると『日日是好日』の題材、森下さんのものでいこう、と思われた?
大森:これはもうほんとに一つ、一番大きいのは「世の中にはすぐ分かるものと、時間をかけてじっくりと分かるものがあるんだ」ということ。
各務:いいテーマですね。
大森:それから、「まずは形をつくって、そこに中身を入れていけばいいんだ」ということ。僕は”形をつくって中身を”というものは実感としてあんまり分かっていないんですよ、今でも。ただ知りたい、という欲求はすごくあったんです。僕は俳優を演出する時、割と「心をつくれ」というところから入るんですよ。だけどこれは、「両方が行ったり来たりしているんじゃないかな」という気がちょっとしていて。心だけでも駄目なんですよ。1回、体をバーッと。俳優さんに動いてもらうと、それだけで俳優さんはテンションが上がって、自分の何かを開放できたりするんです。役者というものは、とにかくもう解放する力とか、リラックスすることがすごく大事で。俳優を扱うということは、人間を扱うことなので。人間たちが今、かなり少し苦しんでる。生きにくい人たちはやっぱり求めてくるんですよね、俳優を通してー…みたいなことで。
『タロウのバカ』、着想から20年経っても変わらないもの
各務:『タロウのバカ』は脚本が大森監督自身で、20代の一番最初に書かれたものですよね。
大森:そうですね。
大森:25年ぐらい経ってる。
各務:25年経った中で新しく映画にして世に出そうと。
大森:最初に撮るような機会はあったんですけど、なかなかいろんな状況でうまくいかなくて。そうこうしてるうちにだんだん僕は他の映画を作っていって。『タロウのバカ』という本は、ストーリーが明確に進んでいく映画ではないし、割と少し暴力的でもあるしで、なかなか撮る機会がなかったんですよ。その時には阪神の震災とか、オウムもあったんですけど、その前に書いてて。
各務:その前なんですか。
大森:僕もその時代を生きていたので、割と敏感な20代前半を生きていたんですけど、やはり「人が本当に亡くなっていくんだ」みたいなことを、初めて感じたんですよ。それで世紀末になって、9.11があって、それから3.11もあるんですけど。その中で、もし”死”というものの捉え方を日本人が変化していったんだとしたら、「もしかしたら『タロウのバカ』という映画を撮らなくてよかったのかもしれない」って今、思うんです。やはり経済の合理性みたいなこと、あるいは、死というもののニオイを消していく力みたいなもの、「戦争は経済を発展させていく」という資本主義のこの論理って、ものすごいんですよね。たぶんやめられないんじゃないのかなという気がするんですよ、もう人間というものが。
各務:止まらないですね。
大森:そう。だから出家するしかないかな、と思うんですけど。
永井:出家してもあるかもしれない。
大森:ありますよね。これに対して、僕ずっと自分なりの疑問を持っていて。それを少し原初的に表してるのが『タロウのバカ』という映画なんですよ。
各務:今もまったく通じていますよね。変化はあまりないように私は思っています。
大森:そう。でも、このタイミングっていうのは、別にほんと偶然で。
大森:それこそ、『日日是好日』でお客さんがいっぱい入ったので、お金が集まりやすくなったという生臭い話もあるんですけど。でも、やはり元はと言うと、僕が二十何年前に書いた本をまだ撮りたいと思えているということが、撮れる原因だと。
各務:変わっていない、変わらぬものですよね。長い間時間をかけても。
大森:それが良いことなのかって、良くないことじゃないかって思うんですけど。
各務:雲門が生きていた唐の時代から何か通じているような気が、今お話を伺っていて思いますけれど。
永井:私も実は修士ですから、24歳で原稿を書いたんですね。それで、本になったのは65歳ぐらいになってからです。40年ぐらい抱っこして。
各務:(監督と)同じぐらい、25前後のところで。

永井:「さぁ、どうしようかな」と思いながら、でも、ずっと持っていると、どこかで熟してくるんですよ。我田引水ですけれども、永平寺を開いた道元禅師の『正法眼蔵』という、岩波文庫本で4冊ぐらいになる書を、我々は学部の頃から読まされるんですけれども、まぁ難解なことおびただしくて。言われるがままに授業で読む。それがやはりある程度の年になって、前に持っていた文庫本を引っ張り出して読むと、何となく少しだけ分かるようになった。それはずっと頭のどこかにあって、行ったり来たりしながら、ちょうど螺旋階段の上に上がるように、道元の心境に到達できるはずもないんだけれど、少なくとも、自分がそういうところを通っているんだな、ということはよくわかりましたね。
各務:雲門の時代からずっと、死をというテーマにしてきましたけれども、大森監督の20代に感じられたこと、今になってもまだ全然フレッシュで、同じようなテーマでも新しくも感じられるくらいです。「あまり変わってない」と、締めくくってよいのかはわからないですが・・・。『日日是好日』でも『タロウのバカ』でも。
永井:若い人って、あぁいうのありますよね。社会の規範とか考え方とはまったく違った。そしてその違っていることに対してイラ立っている、という世界が。それを画像化すればあぁいうバイオレンスな世界になるのかもしれないけれど、それを理解してあげないで言うと何だか暴力的で、「最後わめいておしまいだったぜ」って話になってしまう。
お釈迦様が説いた死と、現代人の死生観
各務:仏教での死のお話で、お釈迦(しゃか)様のことを少しだけ付け加えていただけると。
永井:人間の生きているこの”生”というものは幾つかの要素があって、その要素が集まって、縁によって今のこの命があり、その縁が離れれば死がやってくる。あるいは、縁のバランスが崩れれば病気にもなるし、老いも来る、というのが基本的な考え方なんです。だから「死だからといって、それはたまたま縁が離れただけなのだから、そんなに恐れたりおどおどする必要はないんだ」というのがお釈迦様で。お釈迦様の有名なお話は「毒箭の譬え(どくやのたとえ)」という言い方で、お弟子さんだったと思いますが、「人間死んだらどうなるんでしょう?」と質問するんですね。そうするとお釈迦様自身は経験論者。だから、お釈迦様は「私も実は死んだことがないから、死んだらどこへ行くのか、あの世があるとも言えないし、ないとも言えない。そもそも毒矢が飛んできた時に、”いったい誰が・どんな理由で、それからどんな毒薬を使って射ってきたんだろう?”とか、いろいろな条件を全部クリアできるまで矢を抜くのをよそうといったら、死んでしまうだろう」と言う。つまりそれは「死んだらどうなるかを考えるよりも、今、どう生きるかということを考えて生きなさい」と。理屈的な世界で言うと「人間死ぬのは当たり前でしょ?」という話になるんだけれども、その時に涙を流すのも人間で、そこの部分もお釈迦様は大事にされたという。つまり生きていることが良くて、死ぬことは悪いことなんじゃなくて、五分五分で見ていく。ただ問題は、言うのは簡単だけど、そうはなかなかいかないというのが生きている人間で、みんなそこでもだえ苦しむし、(その葛藤を)突き抜けられるかどうか、ということになっていくんですね。
各務:そうですね。一言ではとても語れないと思います。
永井:それこそ「『般若心経』の色即是空で終わりだ」と言ったらおしまいになってしまいます。そこのところをどういうふうに開いて言っていくかだと。私なんか現場を預かっていることもあるので、余計そう思います。だから涙している人に、それこそ宮沢賢治みたいに「雨ニモマケズ風ニモマケズ」って。泣いている人がいたら、行って慰めてやれというようなあの言い方は、やはりとても大きな意味、宗教者としては考えるべきだろうなと思っています。
各務:そういう意味では、今回の大森監督最新作の『タロウのバカ』は、死生観とよく聞かれますけれども。死についてYOSHIという彼が出てきて。
大森:主人公の。
各務:タロウ君が出てきて、彼が問うていますけれども。そういう意味で、現在にも通じる今の死生観というものが出ているのではないかなと、私は思いました。
大森:難しいですけど、宗教者を前に。
各務:でもあの映画、すごくそういうものを感じさせられました。
大森:僕はやはり、人間という社会を契約上作っていかなきゃ生きていけない弱い動物なんだけど、人間は人間である前に”人”として、ある”生物”としてまずいるじゃないですか。そのことを忘れ過ぎてしまうと、ちょっと逆に生きづらいんじゃないの?という。やはり、生きるっていうことはおっしゃってたように
大森:死と同じようにあって、それで、そのことを忘れ過ぎてしまうと、ちょっと生きづらくなってしまうんじゃないのかな?というふうな思いはずっとあるんですよ。
永井:昔は死が近かったんですね。大きな家に住んで、おじいちゃん・おばあちゃんがいて、両親がいて、孫がいてって。じいちゃんばあちゃんが先に逝くとすれば、もうこれは駄目だ、というとね。
各務:お葬式もありますしね。
大森:見送りですね、横で。
永井:みんなでこんなんふうになって死んでいくのか、という。今はそんなことはありませんけれども、亡くなると、遺体を拭き清めるということを家の人たちがやるわけです。孫はこうやって見るわけです。すると、あの優しかった爺婆が、こうやって死んでいくんだというのを見れば、嘘でも分かる。今は病院で亡くなると、たちまち、火葬場に行ってそれでおしまいという世界があるらしいから。
各務:人ごとになっちゃうんです。
永井:霊柩車がたまに通るぐらいで関係ないですもんね。だけど、「お前も死ぬんだよ」ということをもっと。
各務:現実に思ってね。
永井:「いつ逝くか分からない人生を生きている」という世界を、もっと前に出さないと。
各務:そうだと思います、本当に。
永井:優しさなんて出来てこないんじゃないの、と思うんです。
大森:本当にそう思うんですよ。
各務:全部が人ごとになっちゃいますよね。
永井:人ごとなんですよ。最後、自分の番が来たら慌てふためいて「俺は死にたくない」って。

学生の今はまだ、何も決めずに進んでもいい
各務:それではそろそろ最後になりますが、大森監督には学生の後輩に対して、何か一言メッセージをお願いできたらと思います。
大森:いっぱいお話ししたんですけど、僕はもう”学生たちは、自分ではまだあまり決めずに”ですね。厳しい言い方ですけど、決まったすごい才能がある人は、もう大学なんて来なくてよかったんですよ。大学まで来ているということは、”自分が何者でもない”というところからもう一回。僕もそうだったんです。そこから始める、という。俺はやはり、天才は二十歳で死ぬんだというふうに思ったんですよね。その時に、自分はまだこうやってのうのうと生きているということに、割と「自分はもう才能がない」というふうにすごい挫折を大きく経験して。今、大学生になって送っている時に、あまり焦らずに、いろんな物事にちゃんと共感なんてしなくていいから、「見ればいい」と思うんですよね。みんなちょっと共感し過ぎてるでしょ、今。ちゃんと違うものを世の中では出会っていくもので、すごく大事なのは、共感できるものなんてめったに出会わないんですよ。むしろ出会うのは、みんな分かり合えないという、基本的に分かり合えない人に出会うんですよ。でも、その人たちをどう自分が見つめられるのかということが、社会を生きていく時にすごく大事なことだと俺は思う。映画なんか作っていると、毎回いろんな俳優さんとまったく初対面で、急に密で仕事をするんですけど、その人たちをどう、変な言葉ですけど、ちゃんと”見つめられるか”。”愛を持って見つめられるか”ということをやらないと、すごくケンカになったりするので、それがやはり大事なんですけど、そういうふうにやると結構生きやすい。たぶん、分からない人とそこで。
各務:すぐに分かるわけがないと。
大森:わからないんです。それはゆっくりやればいい。
各務:目の前の人は分かりにくい人かもしれない、と。
大森:そう。それで、なんかちょっと腹立ってしまった時は「自分がまだ小さいからそうなってるんだ」って思うと、ものすごいこういうー…
大森:ちょっと、そういうふうに思う。ただ学生はもう少し大きい意味でいろんな、勉強もそうだけど、それと人間関係もそうだし出会うもの、そのものにゆっくりと大きく触れ合ってほしいな、というふうに僕は思っています。
各務:ありがとうございます。
大森:いえいえ、すみません。なんか真面目になっちゃって。
永井:いやいや、大丈夫です。
各務:本日は本当にお時間を頂きましてありがとうございました。
永井:とってもいいお話でした。
大森:ありがとうございます。
各務:総長も、何か学生に。
永井:おっしゃるとおりで。やはり、破茶滅茶に冒険をしながらー…というのは若さの特権だとよく言われますけれど、いろんなことをトライアルして、自分の一番合ったところへ突き進んで行けるようになれば、それが結果的には良い方向に行くんだとは思うんですが。嫌々やる仕事なんて面白くないだろうし、嫌々生きる人生というのも面白くないでしょう。「これなら誰にも負けない」というものを自分で見つけていくよりしようがないでしょうね。
各務:そのとおりだと思います。それでは本日は、これでインタビューを終わりたいと思います。ありがとうございました。お疲れさまでした。
永井:ありがとうございました。
大森:どうもありがとうございました。
 大森 立嗣
大森 立嗣
映画監督
1970年東京都出身。駒澤大学文学部社会学科卒業。在学中に8ミリ同好会で自主映画の制作を開始。
俳優、助監督を経て、2005年『ゲルマニウムの夜』で初監督としてデビュー。
2010年『ケンタとジュンとカヨちゃんの国』が日本映画監督協会新人賞受賞。2013年、『さよなら渓谷』では、第35回モスクワ国際映画祭にて日本映画として48年ぶりとなる審査員特別賞を受賞するという快挙を成し遂げる。さらには同作と『ぼっちゃん』(2013)でブルーリボン賞監督賞を受賞。『日日是好日』(2018)では、第43回報知映画賞監督賞を受賞する。
その他、『まほろ駅前狂騒曲』(2014)、『セトウツミ』(2016)、『光』(2017)、『母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思った』(2019)、『タロウのバカ』(2019)等、話題作を発表し日本映画界を牽引し続けている。
 永井 政之
永井 政之
駒澤大学総長
1946年群馬県生まれ。2009年4月~2013年3月駒澤大学仏教学部長、2013年4月~2017年3月駒澤大学禅文化歴史博物館長を歴任。2017年3 月31 日定年退職。同年6月駒澤大学名誉教授。2019年10月1日学校法人駒澤大学総長に就任。群馬県良珊寺住職。
専門は、禅学。主な著書として、『中国禅宗教団と民衆』(内山書店)、『雲門』(臨川書店)、論文として、「東皐心越研究序説」(禅宗の諸問題)等がある。
 各務 洋子
各務 洋子
駒澤大学 クローバル・メディア・スタディーズ学部 教授
東京都生まれ。国際基督教大学大学院行政学研究科経営学専攻博士後期課程修了。博士(学術)。米国コンサルティング会社勤務などを経て駒澤大学経営学部教員。同大学グローバル・メディア・スタディーズ(GMS)学部設立に設置準備室長として関わり2008年より現職。
2013年コロンビア大学ビジネススクールにて1年間客員研究員。同学部学部長(2015年4月~2019年3月)。2019年6月より同学学長室学長補佐。主な著書に『映像コンテンツ産業とフィルム政策』(丸善)、『コンテンツ学』(世界思想社)、『トランスナショナル時代のデジタル・コンテンツ』(慶應義塾大学出版会)、『情報通信の国際提携戦略』(中央経済社)、『経営学基礎』(中央経済社)など。

SPECIAL
ZEN,KOMAZAWA,MANAGEMENT
第5回はゲストに小西美術工藝社社長のデービッド・アトキンソンさんを迎え、禅文化歴史博物館の飯塚館長、経営学部の青木先生の3人で『禅とマネジメント』をテーマに鼎談を行いました。 禅においても経営においても、私たちが考えるべき"本質"とはなんなのか。アトキンソンさん視点で伝統文化のあるべき姿についても・・・
2020.08.07

SPECIAL
ZEN, KOMAZAWA, ART
第3回となる今回は、京都の絵描きユニット「だるま商店」の安西さんと、本学仏教学部の村松先生が『禅×アート』というテーマで対談しました。 取材や研究を重ね、時には1つの作品に2年以上もの時間をかけるという安西さんの作品は、その極彩色の見た目のインパクトだけではなく、細部に工夫された“物語”も魅力です・・・
2019.09.17