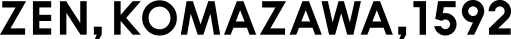禅とマインドフルネスとの比較(5)
5. 自己 -脱中心化と自他一如-
マインドフルネスには、重要な要素として、脱中心化があります。これは、「思考から距離を置くスキル」(杉浦,2008)(※1)や、「思考や感情を、自分自身や現実を直接反映したものとして体験したり、解釈するのではなく、それらを心の中で生じた一時的な出来事としてとらえること」(Teasdale et al., 2002)(※2)とされています。たとえば、ネガティブな思考が生じた場合、そのネガティブな思考は主観的な判断であり、事実ではない一時的な出来事として客観的に距離をおくことで、ネガティブな思考の連鎖に巻き込まれないようにします。そして、主観とは異なる客観的な事実として、回避するのではなく、ありのままに受け入れるという意図的な態度です。マインドフルネスは、思考をコントロールするのではなく、ありのままの現実を受け入れるとしています。しかし、否定的な意図はありませんが、誤解を恐れずに言うのなら、この態度はある意味で客観的にとらえようと、思考のコントロールをしているとも言えます。
禅において、『正法眼蔵』「現成公案」に「自己をはこびて万法を修証するを迷とす。万法すすみて自己を修証するはさとりなり」とあります。これは「自己のはからいであらゆる存在を明らかにしようとしようとするのは迷いである。あらゆる存在が自己だとわかるのが悟りである」ということです。また、同じく「現成公案」に「仏道をならふというは、自己をならふなり。自己をならふといふは、自己をわするるなり。自己をわするるというは、万法に証せらるる。万法に証せらるるといふは、自己の身心、および他己の身心をして脱落せしむるなり」とあります。これは「仏道というのは徹底的に自己を追求することである。自己を追求するとは、自己を忘れることである。自己を忘れるというのは、あらゆるすべてのものに実証されることである。すべてのものに実証されるというのは、自己も他己も独立して存在しているのではなく、互いにつながりを持って存在しているのであり、それがあるがままの姿である」ということです。つまり、無我・縁起・自他一如なのです。
マインドフルネスの脱中心化では、主観にとらわれず、自己とは離れた現実として客観的にとらえることになり、主体と客体との関係がはっきりと分かれます。そして、その客体を言語化することで明確にとらえることが行われます。換言すれば、自己の知的思考よって主体と客体とを明確に分け、自己が独立して存在していることを強調しているとも言えます。
対して、禅では自己のはからいをもって自己を独立したものとしてとらえることが迷いであるとしています。自己は独立しては存在しえません。現実の自己は、あらゆるすべてと一体となって存在しているのです。たとえば、空気は自己の存在とは関係がないと思うかもしれませんが、空気がなければ、自己も存在しないのです。同様に、現実のあらゆるすべてがあるからこそ、自己は存在できているのであり、何かが欠ければその現実・自己は存在しないことになります。したがって、自己と他己とを区別はできても、独立しているのではなく、すべては縁起であり自他一如なのです。
註)
※1 杉浦義典 (2008). マインドフルネスにみる情動制御と心理的治療の研究の新しい方向性 感情心理学研究,16,167-177.
※2 Teasdale, J. D., Moore, R. G., Hayhurst, H., Pope, M., Williams, S., & Segal, Z. V. (2002). Metacognitive awareness and prevention of relapse in depression: Empirical evidence. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70, 275-287.
(つづく)
体と心チーム 文学部 小室央允

SPECIAL
ZEN,KOMAZAWA,MANAGEMENT
第5回はゲストに小西美術工藝社社長のデービッド・アトキンソンさんを迎え、禅文化歴史博物館の飯塚館長、経営学部の青木先生の3人で『禅とマネジメント』をテーマに鼎談を行いました。 禅においても経営においても、私たちが考えるべき"本質"とはなんなのか。アトキンソンさん視点で伝統文化のあるべき姿についても・・・
2020.08.07

SPECIAL
ZEN,KOMAZAWA,MOVIE
第4回はゲストに映画監督の大森立嗣さんを迎え、永井総長、各務教授の3人で監督の作品を中心に『禅と映画』をテーマに鼎談。 本大学のOBである大森監督は、学生時代の環境がとても有り難かったと振り返ります。 監督の作品と禅を絡めながら、人生や人の死について考えさせられる時間となりました。 ※この対談・・・
2020.03.05