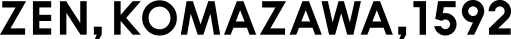上田秋成と禅
上田秋成は怪談『雨月物語』の作家として知られています。この作品中の一篇「青頭巾」は下野国(今の栃木県)の曹洞宗の寺、大中寺を舞台とする、禅宗との関係の色濃い作品です。高徳の僧が晩年、稚児への愛執を募らせ、ついに鬼と化して村人を恐怖に陥れます。どうしようもない業に苦しむ僧(院主)に、快庵禅師という旅の僧が二句の証道歌を授け、「この句の意が解けた時、おまえは本来の仏心に逢うだろう」と教え諭します。一年後、再びかの地を訪れた快庵禅師は、影のような姿になって一心に句を唱えている院主を一喝、禅杖で頭を打つと、院主は氷が朝日に遭うごとくに消え失せてしまいました。快庵禅師は、村人に乞われ、この大中寺の住持となる、というお話です。
この作品の中で特に印象深いのが、院主を諭す言葉、「心放(ゆる)せば妖魔となり、収むる則(とき)は仏(ぶっ)果(か)を得る」でしょう。たとえ一度は道を踏み外したとしても、心を入れ替えて信心すれば、必ずや御仏の教えに救われるであろう、というのです。院主はこの言葉を信じてひたすらに仏道に向かい、鬼となった心を自ら浄化したのです。
さて、秋成の仏教観を表わすこの一節は、最晩年の作品にもう一度現われます。『春雨物語』十篇のうちの最終話、「樊噲(はんかい)」においてです。この作品は、親・兄を殺して故郷伯耆国(今の鳥取県)を出奔、各地を流浪しながら盗賊を働き、悠々と悪党生活を送る主人公、大蔵(のちに樊噲)の一生を描く、一種のピカレスク小説です。豪胆で神をも恐れぬ主人公が、突然雷に打たれたごとくに頓悟したのは、下野国那須野の原の殺生石で一人の無欲の僧に出会ったからでした。自らのあさましさを痛感した樊噲はこの僧の弟子となり、修行の道に入ります。晩年、死の床についた樊噲は「釈迦、達磨も、我もひとつ心にて、曇りはなきぞ」と言い残して大往生、「「心収むれば誰も仏心也。放てば妖魔」とは、この樊噲の事なりけり」と物語は締めくくられます。
忠孝の精神を重んじる江戸時代において、この親殺しの物語と、もう一篇、主君殺しを描く「捨石丸」を断じて許せないという読者もおり、この二作をあえて除いた『春雨物語』の写本も存在しています。しかしこのことは逆に、それほどの大罪人樊噲でさえも達磨と同じ仏心を持っている、人間は過ちを犯す弱い存在であるが、どんな罪深い人間でも心の持ちようで生まれ変われる、と考える秋成の思想を浮き彫りにしているとも言えるでしょう。
仏教に対する批判的な言説も多い秋成ですが、仏教は苦悩する魂を真に救済するものであってほしいと願う、その心の裏返しなのかもしれませんね。
近衞典子

SPECIAL
ZEN,KOMAZAWA,MANAGEMENT
第5回はゲストに小西美術工藝社社長のデービッド・アトキンソンさんを迎え、禅文化歴史博物館の飯塚館長、経営学部の青木先生の3人で『禅とマネジメント』をテーマに鼎談を行いました。 禅においても経営においても、私たちが考えるべき"本質"とはなんなのか。アトキンソンさん視点で伝統文化のあるべき姿についても・・・
2020.08.07

SPECIAL
ZEN,KOMAZAWA,MOVIE
第4回はゲストに映画監督の大森立嗣さんを迎え、永井総長、各務教授の3人で監督の作品を中心に『禅と映画』をテーマに鼎談。 本大学のOBである大森監督は、学生時代の環境がとても有り難かったと振り返ります。 監督の作品と禅を絡めながら、人生や人の死について考えさせられる時間となりました。 ※この対談・・・
2020.03.05